2025年も、自動車保険はダイレクト型(ネット型)を中心に、保険料を抑えつつ十分な補償を受けられるプランが充実しています。
しかし「どれが本当に安くて信頼できるのか」は、はじめての方にとって分かりにくいものです。
そこで保険料の安さ・補償の充実度・利用者満足度を軸に、2025年時点でおすすめの格安自動車保険をランキング形式で紹介します。
第1位:ソニー損保
特徴:保険料・満足度ともに総合トップクラス
- ダイレクト型の代表格。保険料が安く、事故対応満足度も高い
- 安全運転に応じた「走行距離割引」や「30%キャッシュバック制度」あり
- 顧客サポート・ロードサービスも高評価
【こんな人におすすめ】
安さと補償のバランスを取りたい人/はじめて保険を契約する人
第2位:SBI損保
特徴:ネット割引が強く、とにかく保険料が安い
- 若年層やセカンドカー利用者からの人気が高い
- ネット申し込み割引や月払い制度が充実
- 補償内容も比較的柔軟で、自動車保険初心者にも使いやすい
【こんな人におすすめ】
保険料を最優先で安くしたい人
第3位:SOMPOダイレクト(おとなの自動車保険)
特徴:40代〜50代向けの料金設計でお得
- 年齢・運転歴に応じた細かい割引制度が豊富
- 他社と比べても事故対応に定評あり
- 補償のカスタマイズ性も高く、ロードサービスが手厚い
【こんな人におすすめ】
中高年層/運転歴の長い人/補償を柔軟に選びたい人
第4位:アクサダイレクト
特徴:補償の選択肢が幅広く、保険設計がしやすい
- 保険料は抑えつつ、対人・車両補償などを細かく選べる
- 「車両保険なし」「特約を絞る」とさらに安くなる
- 補償の自由度重視派に人気
【こんな人におすすめ】
自分で補償を選びたい人/車両保険をつけない予定の人
第5位:イーデザイン損保
特徴:テレマティクス型で走行距離・運転傾向に応じた割引が魅力
- 走行データを元にした「安全運転スコア」で保険料が下がる
- ドライブレコーダーとの連動サービスあり
- 若年層にも対応しやすい設計
【こんな人におすすめ】
普段の走行距離が少ない人/スマートフォン連携を活用したい人
【保険料を安く抑えるためのチェックポイント】
以下の条件を満たすことで、よりお得な保険料になります:
- 運転者の範囲を限定する(本人・配偶者のみなど)
- 年間走行距離が少ない(5,000km未満など)
- 車両保険をつけない、または限定補償にする
- インターネット割引・無事故割引を活用する
- 20代以下は家族の等級を引き継ぐ(等級継承)
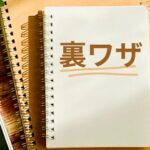

目次
運転者の範囲を限定する(本人・配偶者のみなど)
自動車保険は、誰が車を運転するかによってリスクが変わるため、保険料も大きく左右されます。中でも「運転者の範囲」を明確に限定することで、無駄な補償を省き、保険料を抑えることが可能です。
これはネット型・代理店型どちらの保険でも非常に有効な節約術のひとつです。
1. 運転者の範囲とは?
保険契約時に設定する「この車を運転するのは誰か」の条件のことです。
具体的には、以下のような選択肢があります。
- 本人のみ
- 本人・配偶者
- 本人・配偶者・同居の家族
- 本人・配偶者・同居/別居の親族全体
- 制限なし(誰が運転しても補償対象)
この中で「本人のみ」や「本人+配偶者」に限定するほど、保険料は安くなります。
2. なぜ範囲を狭めると安くなるのか?
- 事故リスクが低くなると判断されるため
→ 限定された運転者は、運転歴が把握しやすく、年齢・経験的にも安定している傾向があるため。 - 保険会社が想定する“賠償リスク”が下がる
→ 例えば、不慣れな別居の家族や友人が運転する可能性を除外すれば、それに対応する保険料も不要になります。
3. 範囲設定による保険料差のイメージ
| 運転者の範囲 | 保険料イメージ(年間) | 備考 |
|---|---|---|
| 本人のみ | 最も安い | 他人に貸すと補償されない |
| 本人・配偶者 | 安い | 日常的に夫婦で使用する場合に有効 |
| 同居の家族も含む | やや高い | 子どもが運転する場合など |
| 制限なし(誰でも運転可) | 高い | 家族や友人への貸与も想定 |
【注意点と失敗しないコツ】
限定しすぎて補償外になるケースに注意
- 例:友人が運転して事故 → 「本人・配偶者のみ補償」の契約では対象外
- 例:成人した子ども(同居)も使うのに「本人のみ」で契約 → 補償されない可能性
こんな場合は見直しを
- 子どもが免許を取得した
- 家族構成が変わった(結婚・同居)
- 車を共有する機会が増えた
4. おすすめの設定パターン
| 利用状況 | おすすめの範囲設定 |
|---|---|
| 単身で通勤・買い物が中心 | 本人のみ |
| 夫婦で共用している | 本人・配偶者 |
| 親子で車を使う(同居) | 本人・配偶者・同居の家族 |
| 車を友人にも貸すことがある | 制限なし(割高になる) |

年間走行距離が少ない(5,000km未満など)
自動車保険では、年間の走行距離も保険料に大きな影響を与える要素のひとつです。
これは走行距離が長ければ長いほど、事故に遭遇するリスクも高まるという統計に基づいており、多くの保険会社が走行距離に応じた保険料体系を採用しています。
特に年間走行距離が5,000km未満のような“短距離ユーザー”であれば、保険料を大幅に抑えることが可能です。
1. なぜ走行距離が少ないと保険料が安くなるのか?
保険会社は「走る時間が少ない=事故リスクが低い」と判断するためです。
交通事故の多くは「運転している時間・距離」と比例する傾向があるため、
以下のような構造になります:
- 走行距離が短い → 運転の頻度が低い
- 運転頻度が低い → 事故リスクが下がる
- 事故リスクが低い → 保険料が安くなる
2. 主な距離区分と割引傾向(例)
| 年間走行距離の目安 | 割引率の傾向 | 主な対象者例 |
|---|---|---|
| ~3,000km | 非常に安くなる | 買い物・週末ドライブ程度 |
| ~5,000km | 比較的安くなる | 通勤なし・使用頻度低め |
| ~7,000~9,000km | 一般的な水準 | 通勤あり・月2~3回遠出 |
| ~12,000km以上 | 高めの保険料になる | 営業・頻繁な遠距離運転 |
※距離区分は保険会社によって異なりますが、おおむね上記のような分類が一般的です。
3. 距離連動型プラン(テレマティクス型)の導入も拡大中
一部のダイレクト型保険では、走行距離をリアルタイムで計測し、
実際の運転状況に応じて保険料を調整する「距離連動型」「走行データ連携型(テレマティクス)」も増えています。
- ソニー損保:年間走行距離を申告し、予測距離より短ければ次年度の割引につながる
- イーデザイン損保(&e):専用アプリが距離・運転傾向を記録し、優良運転で割引
【申告時の注意点と失敗例】
【注意点】
- 実際より過少に申告すると、超過した場合に補償が受けられないリスクがあります
- 距離が年ごとに大きく変動する場合は「やや多めに申告」しておくのが安全
【よくある失敗】
- 「通勤しないから3,000kmで大丈夫」と申告 → 思ったよりドライブが増えて超過
- 契約時に安さだけを優先 → 年間1万km超で結局追加料金や割引適用外に
4. おすすめの人・向いている使い方
年間5,000km未満で済む人に特におすすめ:
- 普段は公共交通機関を使い、車は週末のみ利用
- 高齢の方で運転頻度が少ない
- 家族共有車をたまに使う程度
- リモートワーク中心で通勤が不要な会社員


車両保険をつけない、または限定補償にする
自動車保険の保険料を構成する中で、最も金額に差が出やすいのが「車両保険」です。
補償内容が広くなるほど保険料は上がりますが、実はこの車両保険の設定を見直すことで、年間1万〜数万円の節約も可能になります。
車の価値や使用目的に応じて、車両保険を“つけない”あるいは“限定的な補償にする”ことが効果的な選択肢となります。
1. 車両保険とは?
契約車両に対して「自分の車が損害を受けた場合」に補償する保険です。
対象となる損害の例:
2. なぜ車両保険なし・限定補償で安くなるのか?
車両保険は補償対象が広いため、以下の理由から保険料が大きく上がります:
- 高年式・高額車は保険金額が高く設定される → 保険料が高くなる
- 補償の範囲が広い → リスク料率が上がる
- 免責金額(自己負担)を下げると保険料も高くなる
したがって、車両保険を外す or 範囲を狭めることで、その分の保険料がカットされ、保険料が大幅に安くなります。
3. 車両保険の代表的な設定タイプ
| タイプ | 補償内容 | 保険料 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 付けない | 補償なし | 最安 | 古い車・修理費より乗換優先の人 |
| 限定タイプ(エコノミー) | 他車との衝突、火災・盗難のみ補償 | 安い | 安く抑えたいが最低限は備えたい人 |
| 一般タイプ(フルカバー) | 自損・当て逃げ・自然災害など含む | 高い | 新車・高額車・ローン中の車など |
4. 「車両保険なし」でも安心できるケースとは?
以下のようなケースでは、あえて車両保険を外す判断が有効です:
- 購入後10年以上経過した車(時価価値が低い)
- 事故を起こしたら買い替えを前提としている
- 中古で購入し、修理より廃車が現実的
- 通勤・通学などで短距離しか使わない
このような場合、車両保険を付けても「修理費より保険金のほうが低い」こともあるため、コストメリットが薄くなります。
5. 「限定タイプ(エコノミー型)」の使い方と注意点
「車両保険は少しは付けておきたいが、フル補償は高すぎる」という方には「エコノミー車両保険」がおすすめです。
主な補償範囲(会社によって差はあります):
- 他車との衝突による損害(単独事故や当て逃げは対象外)
- 火災・盗難・台風などの災害
- 落書き・いたずら(一部対象)
【注意点】
- 自損事故・当て逃げ・逆突などの補償は原則なし
- 過失割合の大きい事故には非対応の場合もある
- 保険金が支払われない条件を必ず確認することが重要
6. 選び方のポイント
| 状況・希望 | 選択すべきタイプ |
|---|---|
| 保険料最優先・古い車 | 車両保険なし |
| 安さ重視+最低限の補償が欲しい | 限定(エコノミー)タイプ |
| 新車・高額車・ローン返済中 | 一般(フルカバー)タイプ |

インターネット割引・無事故割引を活用する
自動車保険をお得に契約するためには、補償の削減や運転条件の見直しだけでなく、「割引制度」をしっかり活用することが欠かせません。特にインターネット経由での申し込みと無事故継続による等級アップは、多くの保険会社が提供している主要な割引制度であり、簡単かつ確実に保険料を安く抑えることができます。
1. インターネット割引とは?
【概要】
オンライン経由で自動車保険を契約または更新することで適用される割引制度。
主にダイレクト型(ネット型)保険会社が導入しており、最大で1万円以上の割引が受けられるケースもあります。
【特徴】
- 書類郵送・対面手続きが不要
- 24時間申し込みが可能
- 手数料や人件費が削減されるため、その分が保険料に反映される
【主な割引額の目安】
| 保険会社名 | 初回インターネット割引 | 更新時の割引 |
|---|---|---|
| ソニー損保 | 最大10,000円 | 継続で2,000円程度 |
| SBI損保 | 最大12,000円 | 継続でもあり |
| チューリッヒ保険 | 最大10,000円 | 継続は割引なしもあり |
2. 無事故割引(ノンフリート等級制度)とは?
【概要】
無事故で1年間保険を継続することで、翌年の等級が1段階アップし、保険料が割引される制度です。
一般に、自動車保険の等級は1等級(最も高い保険料)から始まり、20等級(最大割引)まで成長します。
【等級による保険料の違い】
| 等級 | 割引率(目安) | 特徴 |
|---|---|---|
| 6等級 | 新規契約者(割引なし) | 初回契約時の一般的等級 |
| 10等級 | 約40%割引 | 無事故継続4年程度で到達 |
| 20等級 | 約63%割引 | 最上位クラス。事故歴なし |
【ポイント】
- 1年無事故 → 1等級UP(保険料が安くなる)
- 事故あり → 通常3等級DOWN(保険料が高くなる)
- 同じ保険会社でなくても「等級」は引き継げる(中断証明書があれば5年まで保存可能)
3. ダブル活用でさらにお得に
インターネット割引と無事故割引を同時に活用すれば、以下のような効果が期待できます。
【例:新規契約時】
- 保険料:年間80,000円(等級6・初契約)
- インターネット割引:▲10,000円
- 翌年、無事故で等級アップ → 約7,000円の保険料ダウン
→ 2年目には実質17,000円の差額になることもあります。
【注意点と活用アドバイス】
インターネット割引の注意点
- 一部の代理店型保険では適用されない
- 書類での申し込みに切り替えると割引対象外になる場合がある
- 初回のみ適用、継続時は割引なしの保険会社もある
無事故割引の注意点
- 軽微な物損事故でも「事故あり扱い」になることがある
- 1回の事故で一気に等級が下がると、保険料が翌年から数万円上がるケースも
- 保険会社によっては「事故有係数」が適用され、復活に3年以上かかる場合もある
【こんな方は特に活用すべき】
- ネット操作に抵抗がない方:インターネット割引の恩恵が大きい
- 過去に事故がなく、安全運転を継続している方:等級アップで確実に得をする
- 保険を乗り換えたい方:インターネット経由で新規契約すれば割引の対象に
20代以下は家族の等級を引き継ぐ(等級継承)
20代以下のドライバーが新たに自動車保険に加入する場合、通常は「6等級(割引なし)」からのスタートとなり、保険料が非常に高くなる傾向にあります。しかし、家族の等級を引き継ぐ「等級継承(等級引き継ぎ)」を活用することで、初年度から割引のある等級で契約することができ、大幅な保険料節約につながります。若年ドライバーが保険に入る際には、まずこの制度の活用を検討するべきです。
1. 等級継承(引き継ぎ)とは?
【制度概要】
等級とは、自動車保険の割引率に関わるランクのこと。1等級~20等級まであり、等級が高いほど保険料の割引率も高くなります。
「等級継承」とは、家族が使用していた等級(例:16等級、20等級など)を、別の家族がその車を引き継いで契約する際にそのまま受け継げる仕組みです。
2. 等級継承の対象者
以下のような親族関係にある人の間で等級の引き継ぎが可能です:
- 同居の親族(父母、祖父母、兄弟など)
- 配偶者
- 子ども(同居・別居いずれも可能)
※ただし、継承元が保険を中断または終了することが前提条件です。
3. なぜ20代以下におすすめなのか?
若年層は「事故リスクが高い」と見なされるため、以下のようなデメリットがあります:
- 通常は6等級スタート(割引なし)
- 年齢条件により保険料が高額(特に18〜24歳)
ここで親や祖父母の高等級(例:18等級)を引き継げば、初年度から40〜60%割引が適用され、保険料が半額以下になるケースもあります。
【等級継承の条件と手続き】
【主な条件】
- 保険を引き継ぐ人が同一の車両または名義変更を伴う車両を使用すること
- 継承元の契約者が保険を解約、もしくは別車に乗り換えるなどでその等級を使わなくなること
- 保険会社が同一である必要はないが、条件によっては引き継ぎ不可のケースもある
【手続きに必要なもの】
- 継承元・継承先それぞれの本人確認書類
- 継承元の保険証券または中断証明書
- 車検証(名義確認のため)
4. 等級継承が可能な例・不可能な例
| ケース | 継承できる? | 備考 |
|---|---|---|
| 父が使っていた車を、息子が使用する(名義変更あり) | 可能 | 同居・別居ともにOK |
| 祖母の車を孫が引き継ぐ(名義変更あり) | 可能 | 同居親族ならOK |
| 兄が使っていた車を、弟が引き継ぐ | 可能 | 同居の兄弟ならOK |
| 友人の車を引き継ぐ | 不可 | 血縁・婚姻関係でないため |
【等級継承を使う際の注意点】
- 継承元の保険契約は終了が前提
→ 同時に2人で等級を共有することはできません - 20等級までの積み上げには、無事故継続が必要
→ 継承後に事故を起こすと、せっかくの高等級が下がる - 中断証明書(5年間有効)を発行しておくと将来の再開にも便利
5. どれくらい安くなるか?(目安)
| 等級 | 割引率(目安) | 年間保険料の変化(例) |
|---|---|---|
| 6等級 | 割引なし | 年間12万円(20代男性) |
| 16等級 | 約50%割引 | 年間6万円台まで軽減可能 |
車種や年齢条件によって差はありますが、年間で5万〜8万円の差が出ることもあります。


