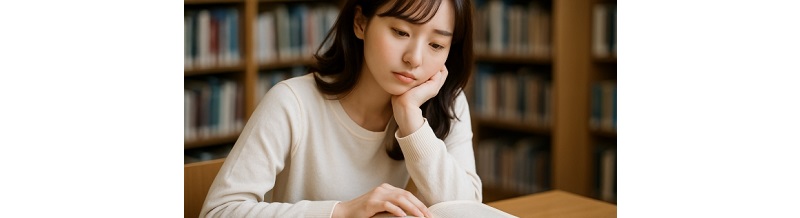大学生や専門学生などが自動車保険に初めて加入する場合、「とにかく安くしたい」という思いが先行しがちです。しかし、補償を削りすぎると、事故時に多額の自己負担が発生する可能性があります。
2025年現在では、ネット型保険の進化や割引制度の拡充により、学生でも納得のいく価格で加入できる選択肢が増えています。
本記事では、学生が保険選びで押さえるべきポイントと、コスパの良い構成例をわかりやすく解説します。
■ 学生が自動車保険で直面しやすい課題
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 年齢リスク | 若年層は事故率が高く、保険料が高額になる(全年齢・21歳未満補償が必要なケース多) |
| 初契約=6等級スタート | 割引がないため、どうしても高くなりがち |
| 保険知識が乏しい | 内容を把握できず、割高なプランを選びやすい |
| 経済的な余裕が少ない | 高額な保険料が学費や生活費を圧迫する可能性あり |
■ 学生向け格安プランを実現する5つの戦略【2025年版】
1. ネット型保険を活用する
2. 家族の保険を引き継ぐ(等級継承)
- 親が使っていた保険の等級(無事故年数)を子どもへ引き継げる制度
- 6等級 → 12等級などになると保険料が半額近くに安くなることも
- 継承は一度きり/同居・扶養内など条件あり
3. 年齢・運転者の条件設定を最適化
- 「本人限定」「21歳以上補償」など範囲を絞れば保険料は大幅に下がる
- ただし、他人の運転や未成年の友人が使う場合は補償範囲に注意
4. 車両保険は原則つけない or 限定型を選ぶ
- 中古車・購入価格が安い車なら、車両保険を外すか「エコノミー型(盗難・火災のみ)」でOK
- 車両保険を省略することで、年間1.5〜3万円の削減効果
5. 特約は“使う可能性があるもの”に限定
おすすめは以下の2つだけ:
- 弁護士費用特約(もらい事故対応)
- ロードサービス特約(レッカー・バッテリー上がり)
■ 学生向けおすすめ保険構成例(2025年想定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険会社 | ネット型(アクサダイレクト、チューリッヒなど) |
| 対人賠償 | 無制限(必須) |
| 対物賠償 | 無制限(必須) |
| 人身傷害 | 3,000万円(推奨) |
| 車両保険 | なし(中古車前提)or 限定型 |
| 特約 | 弁護士費用+ロードサービス |
| 年齢条件 | 21歳以上補償(可能なら) |
| 運転者限定 | 本人限定または家族限定 |
| 年間保険料目安 | 約60,000円〜90,000円(条件により変動) |
■ よくある学生の失敗例と回避法
| 失敗 | 解説と対策 |
|---|---|
| 保険料が高いからといって補償を削りすぎる | 対人・対物は必ず無制限に設定すること |
| 車両保険をつけたまま高額なプランに | 中古車や軽自動車なら原則不要。外すか制限型に |
| 特約をつけすぎて高額に | 「弁護士費用」「ロードサービス」だけに絞る |
| 自分で比較せず親任せ・代理店任せ | ネット型なら自分で見積もり・契約ができて節約しやすい |
【保険料を抑える追加テクニック】
- 早期契約割引:満期の30日以上前の申込で数千円安くなる保険会社もあり
- 複数年契約型プラン:2年・3年の長期契約で年あたりの保険料が抑えられる場合あり
- 運転者の事故歴を記録するアプリ型保険(テレマティクス保険):安全運転で翌年割引に





ネット型保険を活用する
学生が自動車保険に加入する際に直面する最大のハードルは「保険料の高さ」です。運転経験が浅く、事故リスクが高いとされる若年層は、どうしても保険料が割高になります。
しかし、ネット型保険(ダイレクト型保険)を活用すれば、無理なく安心できるプランを安価に組むことが可能です。
ここでは、学生にネット型保険が向いている理由と、活用時の注意点を詳しく解説します。
■ ネット型保険(ダイレクト型)とは?
- 保険代理店を通さず、契約者がインターネット上で直接契約する保険
- 電話や対面の相談なしでも申込・見積もり・変更がすべてWebで完結
- 主な保険会社:ソニー損保、アクサダイレクト、イーデザイン損保、チューリッヒ保険など
■ なぜ学生にネット型保険が向いているのか?
1. 保険料が安い(代理店型より年間1~2万円以上安くなることも)
- ネット型は人件費や店舗運営費がかからず、中間コストを省いているため割安
- 同じ補償内容でも、ネット型なら学生でも月額5,000円前後に収まることも多い
2. インターネット割引がある
- ネット型の保険会社では、Web上で見積もり・契約を完結させるだけで割引が適用
- 初年度は5,000円〜最大1万円前後の割引が期待できる
3. 若年層向けの簡易操作・サポート体制がある
- スマホやPCに慣れている学生世代にとって、専用アプリやマイページの使いやすさは大きなメリット
- 最近はチャット・LINE・メールでのサポートも充実し、「分からない」「不安」にも対応
4. 見積もりがすぐでき、比較もしやすい
- 公式サイトで「車種・年齢・条件」を入力するだけで30秒〜3分で概算保険料が表示される
- 同じ条件で複数社を比較しやすく、自分にとって最も安いプランを選びやすい
【ネット型保険利用時の基本的な流れ】
- 保険会社の公式サイトで無料見積もり
- 条件を入力(車種・年齢・補償範囲・特約など)
- 表示された見積もり内容を確認・比較
- クレジットカードなどでWeb契約を完了
- 保険証券が後日郵送 or PDFで発行される
■ 学生におすすめのネット型保険会社(2025年時点)
| 保険会社名 | 特徴 |
|---|---|
| ソニー損保 | 初心者向けの説明が丁寧/口コミ満足度が高い |
| イーデザイン損保 | 安全運転診断アプリあり/事故対応評価が高い |
| アクサダイレクト | 見積もり・契約がスムーズ/割引制度が豊富 |
| チューリッヒ保険 | 割安プランの幅が広くカスタマイズしやすい |
■ ネット型保険を使う際の注意点
| 注意点 | 解説 |
|---|---|
| すべて自己判断で設計する必要がある | 補償内容を間違えると「必要な補償が抜けていた」という事態も。事前に最低限の知識を得ておくこと |
| 対面での相談ができない | 電話・チャット相談はあるが、代理店のような「担当者常駐型サポート」はなし |
| 入力ミスで条件が狂う可能性がある | 使用目的・年齢条件などを正確に入力することが重要(虚偽申告は保険金不払いの原因に) |
家族の保険を引き継ぐ(等級継承)
学生が自動車保険に初めて加入する際、「6等級(標準)」からスタートするのが一般的です。ところが、等級が低いため割引がなく、どうしても保険料が高額になりがちです。
そこで活用したいのが、「家族の保険を引き継ぐ(等級継承)」という方法です。これは、親や祖父母が使っていた自動車保険の等級を学生本人に移すことで、スタートから高い割引率を得られる制度です。
正しく使えば、年間で数万円単位の節約につながる強力な節約戦略です。
■ 等級継承とは?
- 家族が使っていた自動車保険契約の「ノンフリート等級(割引率)」を、別の家族名義の新規契約に引き継げる制度
- 一度限りの制度で、学生本人名義で新しく保険契約を始めるときに限り使える
■ 等級継承のメリット
| 項目 | メリット内容 |
|---|---|
| 保険料が安くなる | 12等級以上を継承すれば、初年度から30%以上の割引が適用されるケースも |
| 高割引でスタートできる | 通常6等級(割引なし)→ 親の15等級(約50%割引)なら、年間数万円安くなる可能性あり |
| 学生でも入りやすい | 家族との連携次第で、初めての契約でも割引条件を得られる |
■ 等級継承できる対象と条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 継承できる人の関係 | 親・配偶者・祖父母・同居の兄姉など同居または扶養関係がある家族が対象 |
| 継承できる保険契約 | 家族名義の任意保険で、解約・満期・譲渡予定の契約が必要(現在進行中の契約は移せない) |
| 継承のタイミング | 家族の保険を終了し、新たに学生本人名義で契約開始するタイミングでのみ可能 |
| 一度きりの制度 | 一生に一度しか使えないため、タイミングの見極めが重要 |
■ 等級継承の例(保険料の違い)
| 比較条件 | 等級 | 年間保険料(目安) |
|---|---|---|
| 通常の新規加入(20歳・6等級) | 割引なし | 約12〜14万円 |
| 家族の15等級を継承 | 約50%割引 | 約6〜7万円前後 |
※車種、使用目的、条件により異なります
■ 等級継承の注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 継承は1回限り | 他の兄弟に後から譲ることはできない(奪い合いになりやすい) |
| 親の保険は終了させる必要がある | 「親が車を手放す/保険を解約する」前提が必要 |
| 保険会社間で手続きが異なる | 事前に継承予定の保険会社と、新規加入予定の保険会社に相談と確認が必要 |
| 住所変更や扶養証明の提出が求められる場合あり | 同居・扶養関係の証明が求められることがある |
【等級継承が向いている学生のケース】
- 実家の車を譲り受ける予定の大学生・専門学生
- 車を新しく買うタイミングで、親が車を手放す予定
- 就職・進学で独立するが、保険料を大きく抑えたい
■ 等級継承を活用したプラン構成例(20歳・初契約)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 保険名義 | 学生本人 |
| 等級 | 親の15等級を引き継ぐ |
| 対人・対物補償 | 無制限 |
| 人身傷害 | 3,000万円以上 |
| 車両保険 | なしまたは限定型(中古車想定) |
| 特約 | 弁護士費用、ロードサービスなど最小限 |
| 保険料 | 年間 約6〜7万円(条件次第でさらに割引あり) |

年齢・運転者の条件設定を最適化
自動車保険は「どういう人が運転するか」によって保険料が大きく変わります。特に学生は年齢が若く、事故リスクが高いと判断されるため、補償条件を広げすぎると一気に保険料が跳ね上がります。
しかし、正しい条件設定をすれば、年間で2万〜5万円以上の節約も可能です。ここでは、学生が押さえておくべき「年齢条件」と「運転者限定条件」の最適な設定方法を詳しく解説します。
■ 年齢・運転者の条件設定とは?
自動車保険には、どの年齢の人が運転しても補償されるか、どの範囲の人が運転しても保険が適用されるかを定める設定項目があります。
■ 年齢条件の選び方(保険料に直結)
| 年齢条件区分 | 補償対象 | 保険料の傾向 |
|---|---|---|
| 全年齢補償 | 何歳でも補償対象 | 最も高額(学生向きではない) |
| 21歳以上補償 | 21歳以上のみ補償 | 若干割安(学生の中心層に多い) |
| 26歳以上補償 | 26歳以上のみ補償 | 学生には基本不適(保険料は安いが適用外が多い) |
● 学生に最も多いケース
- 大学生・専門学生:20~24歳 → 「21歳以上補償」が最適
- 20歳未満の場合 → 「全年齢補償」を選ばざるを得ず、保険料が大幅に上がる
■ 運転者の範囲(限定条件)の選び方
| 運転者限定条件 | 補償対象 | 保険料の傾向 |
|---|---|---|
| 限定なし | 誰が運転しても補償 | 最も高額 |
| 家族限定 | 同居の家族のみ補償 | 中程度 |
| 本人+配偶者限定 | 自分と配偶者のみ補償 | やや安い |
| 本人限定 | 自分のみ運転時に補償 | 最も安価(学生に最適) |
- 自分だけが車を運転するなら、「本人限定」にすることで保険料が大きく下がる
- 実家の車を家族と共有する場合などは、「家族限定」にする必要あり
■ 条件設定を最適化した場合の保険料差(目安)
| 条件パターン | 年間保険料(参考) |
|---|---|
| 全年齢補償+限定なし | 約13〜15万円 |
| 21歳以上補償+本人限定 | 約6〜8万円 |
| 21歳以上補償+家族限定 | 約8〜10万円 |
■ 学生が設定ミスしやすいポイントと対策
| ミス例 | 解説 | 対策 |
|---|---|---|
| 年齢条件を広げすぎる | 実際は自分だけ運転なのに「全年齢補償」にして保険料が高騰 | 21歳以上補償で十分なケースが多い |
| 限定を付けなかった | 「友人も運転するかもしれない」と不安で「限定なし」に → 年間数万円高くなる | 基本は「本人限定」。どうしても他人に貸すなら1日保険を使う方法もあり |
| 家族限定にして同居していない兄弟が運転 → 補償対象外に | 家族限定=同居の親族が原則 | 条件に合わない人が運転する可能性があるなら「限定なし」か1日保険の併用を検討 |
【条件設定に迷ったときの判断フロー(学生向け)】
-
車を運転するのは自分だけか?
→ はい →「本人限定」
→ いいえ(親や兄弟も運転)→「家族限定」 -
年齢は21歳以上か?
→ はい →「21歳以上補償」
→ いいえ →「全年齢補償(保険料高くなる)」 -
どうしても他人に運転させる必要があるか?
→ たまにある → 限定せず、または1日自動車保険を併用
→ まったくない → 限定ありでOK

車両保険は原則つけない or 限定型を選ぶ
自動車保険の中でも、保険料を大きく左右するのが「車両保険」の有無です。学生は中古車や比較的安価な車に乗るケースが多く、車両保険をフルでつけてしまうと、年間保険料が一気に高額になる可能性があります。
そのため、学生が無理なく保険料を抑えるためには「車両保険は原則つけない」または「限定型(エコノミー型)」に抑えることが効果的です。
■ そもそも車両保険とは?
- 自分の車が事故・災害・盗難などで損害を受けた場合に、その修理費や補償を受けられる保険
- 基本補償(対人・対物・人身傷害など)とは別に任意で付帯する
- 一般的に「補償が広い=保険料が高い」
■ 学生にとってフル車両保険が不向きな理由
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 車の価値が低い | 学生は中古車や軽自動車を利用することが多く、保険金額に対して保険料が割高になる傾向 |
| 修理より買い替えを選ぶことが多い | 数万円の修理費であれば自費で済ませ、保険を使わず等級を守るケースが多い |
| 保険料が大幅に上がる | フル補償の車両保険は、年間保険料を2〜5万円以上押し上げる要因となる |
■ 学生におすすめの車両保険の取り扱い方
◎ 原則:車両保険は「つけない」
- 事故リスクはあるが、車両保険なしでも対人・対物・人身補償はカバーできる
- 「古い車・中古車・軽自動車」なら、修理代よりも保険料の方が高くつく可能性も
◎ どうしても不安な人は:「限定型(エコノミー型)」を選択
| エコノミー型とは? |
|---|
| 対象を「相手車との衝突事故」や「盗難・火災・落書きなどの災害被害」に限定したタイプの車両保険。自損事故(電柱に衝突など)は補償されないが、保険料は大幅に抑えられる。 |
■ 車両保険をつけるか判断する基準
| 条件 | 推奨方針 |
|---|---|
| 中古車(購入価格が50万円以下) | 原則つけない |
| 新車/ローン付きの車 | エコノミー型または一般型を検討 |
| 通学・バイトなど日常使用メイン | つけない(自損事故のリスクを管理) |
| 長距離移動・夜間運転が多い | エコノミー型を検討 |
■ 車両保険を外した場合の保険料差(イメージ)
| 車種・条件例 | フル車両保険あり | 車両保険なし |
|---|---|---|
| 軽自動車(中古) | 約12万円/年 | 約6.5万円/年 |
| コンパクトカー(5年落ち) | 約14万円/年 | 約7.5万円/年 |
実際の金額は条件により変動しますが、年間で5万円前後の差が生まれることも珍しくありません
■ 車両保険を外した場合の補償リスクと対策
| リスク | 対策例 |
|---|---|
| 自損事故の修理費が自己負担になる | 車両保険分の保険料を「積立」として別に管理しておく(万一の修理代に備える) |
| 盗難や自然災害での全損時に補償なし | エコノミー型で「火災・盗難・台風」だけをカバーする設計にする |


特約は“使う可能性があるもの”に限定
自動車保険には、基本補償(対人・対物・人身傷害など)に加えて、さまざまな「特約(オプション補償)」を追加することができます。
しかし、特約をやみくもに付けると、保険料がどんどん高くなり、学生にとっては大きな負担になります。
だからこそ、「本当に使う可能性があるもの」に特約を限定することで、安心と節約の両立が可能です。以下では、学生が付けるべき特約・付けなくてもよい特約を明確に整理してご紹介します。
■ そもそも特約とは?
- 基本補償に追加して契約できる「オプション的な補償」
- 事故時の不安をカバーするものから、利便性向上のためのものまでさまざま
- 1つあたり年間数千円〜数万円の保険料加算になる場合がある
■ 学生におすすめの「最低限つけるべき特約」
1. 弁護士費用特約(強く推奨)
- 相手に過失がある事故(もらい事故)で、交渉が進まない場合の法律相談・弁護士費用を補償
- 加害者が保険未加入・連絡がつかない場合などに非常に心強い
保険料目安:年間 約1,000〜3,000円
なぜ必要?
- 学生は法的交渉に慣れておらず、もらい事故時に自分で交渉するのは非常に難しい
2. ロードサービス特約(必要に応じて)
- バッテリー上がり・パンク・レッカー移動などに対応
- 近年では多くのネット型保険に標準装備されているが、補償内容を確認しておくと安心
保険料目安:年間 約1,000〜2,000円(または無料の場合あり)
なぜ必要?
- 学生は遠出や夜間運転で立ち往生することがあり、トラブル対応が自力では難しい
■ 学生には「原則不要」と考えられる特約(状況により判断)
| 特約名 | 解説 | 基本方針 |
|---|---|---|
| 車両全損時諸費用特約 | 車が全損したときの買い替え手続き費用を補償 | 中古車・安価な車なら不要 |
| 入院時一時金特約 | 入院すると一定額の一時金が出る | 学生は医療保険や健康保険で十分対応できるケースが多い |
| 代車費用特約 | 修理中の代車費用を補償 | 通学に絶対車が必要な場合以外は不要 |
| 個人賠償責任特約 | 自転車事故や日常生活の損害をカバー | 学校・親の保険でカバーされている場合もあるので重複に注意 |
■ 特約をつけすぎるとどうなる?
- 年間保険料が5,000円〜15,000円以上高くなる
- 実際には使わないまま契約を続けている人が多い(=無駄)
■ 「特約は必要最小限」に絞る具体例(学生・軽自動車)
| 特約 | 付帯 | コメント |
|---|---|---|
| 弁護士費用特約 | 付ける | 万が一のもらい事故に備える |
| ロードサービス | 付ける(無料なら◎) | 遠出やバイト先でのトラブルに備える |
| 代車費用特約 | 付けない | 通学に車が必須でなければ不要 |
| 車両無過失事故特約 | 付けない | 被害者になった際の補償が気になる場合に限定 |
| 個人賠償責任特約 | ケースバイケース | 自転車保険で代用されていれば不要 |
【特約の選び方フロー(学生用)】
- 誰かと事故交渉をする自信がないか?
→ はい → 弁護士費用特約を付ける - 車のトラブルがあったとき、自分で対応できるか?
→ いいえ → ロードサービス特約を付ける - 車がないと通学・通勤が成り立たないか?
→ はい → 代車費用特約も検討 - 親や学校の保険で他の補償がついていないか確認
→ 重複がなければ個人賠償責任特約なども検討